グローバル大手DSPのThe Trade Desk(TTD)が実施した「動画配信サービス利用実態調査」の結果が公表された。日本国内在住の2806名を対象にしたアンケート調査には、YouTube、Netflix、TVerといった主要な動画配信サービスに対するユーザーの意識と行動に関する知見が詰まっている。本調査からどのような示唆を導き得るかについて、TTD社に話を聞いた。
(聞き手:ExchangeWire Japan長野雅俊)
「動画配信サービスには支払わない」がほぼ半数
―改めて自己紹介をお願いします。
The Trade Desk の日本担当ゼネラルマネージャーを務める馬嶋慶です。2020年6月の着任以来、「オープンインターネットを対象とした透明性の高いプラットフォームの構築」という当社の理念をさらに浸透させるべく、顧客や社内との積極的なコミュニケーションを図ってきました。その過程を通じて把握した様々な課題に対しては、現在も試行錯誤を繰り返しながら取り組んでいる最中です。
―貴社は昨年末に「動画配信サービス利用実態調査」を発表しました。本調査を実施するに至った背景をお聞かせください。
当社のDSPは動画広告に大きな強みを持っています。動画配信サービスの動向には以前から注目していましたが、本社を置く米国と比較すると、日本の市場はまだまだ拡大の余地が大きい。とりわけ、テレビをインターネットに接続したコネクテッドTV(CTV)市場は日本ではまだ創世期です。現時点における動画コンテンツの消費のあり方や主な動画サービスに対するユーザーの意識を把握することで、デジタルマーケティング全般への示唆を得たいと考えました。
―調査を実施してみて、意外な結果はありましたか。
疑問を感じるような調査結果はあまりなく、例えば「若年層はPCではなく、スマートフォンで動画のコンテンツを消費する傾向が強い」など、この業界では以前から言われてきたことが改めて数値化されたという印象です。
意外な結果と言えば、「動画配信サービスのサブスクリプション費用を支払う場合、毎月最大で、合計いくらまでなら支払えるか」という質問に対する回答です。回答者のほぼ半数が「動画配信サービスに支払おうと思わない」との考えを示しました。
 資料提供: The Trade Desk
資料提供: The Trade Desk
既にNetflixを始めとする有料サービスが世界中で広まっており、また私自身は好きなコンテンツを視聴するためであれば課金を厭わないので、意外でした。日本のユーザーは恐らく地上デジタルテレビ放送やAVOD(広告付き動画配信)に慣れているのでしょう。課金に対してこれほど厳しい評価が示されるとは思っていませんでした。
UGCとOTTを区別する理由とは
―本調査では「個人が制作し、アップロードしたコンテンツ」を「ユーザー作成コンテンツ(UGC)」、「インターネットに接続された端末で視聴可能な、放送局などのプロが製作したプレミアムな動画コンテンツ」を「オーバー・ザ・トップ(OTT)」とそれぞれ定義して、両者を明確に区別しています。

資料提供: The Trade Desk
個人が制作したユニークな動画を視聴できるというのがUGCの魅力ではありますが、一方でそれらの中にはテレビ録画を無責任に投稿しただけのものも少なくありません。コンテンツの質において、著作権が適切に管理された、質の高いプレミアムな動画コンテンツを制作するプロの事業者のコンテンツを広告主はよりブランドセーフなプラットフォームと認識し、UGCプラットフォームとは差別化していることから、当社ではUGCとOTTを区別しています。
―区別した結果、UGCユーザーとOTTユーザーで異なる傾向が明らかになりました。
例えば、UGCユーザーとOTTユーザーでは利用する視聴端末がやや異なります。UGCは62%がスマートフォンでCTVは12.6%、OTTは46%がスマートフォンでCTVは24%です。一般的にOTTは長尺かつプレミアムなコンテンツを放映するので、大きなスクリーンを用いて動画視聴に専念するユーザーの割合が高くなるのでしょう。
自社の製品やサービスを音声付きで大画面を通して宣伝したい広告主にとっては、UGCよりもOTTプラットフォームの方が適していると言えるのかもしれません。
またOTTとUGCでは、どちらが良い悪いではなく、放映される広告の種類や質が異なります。両者の違いは思いのほか多岐にわたるというのが実感です。
―放送局などのプロが製作したコンテンツであれば、地上デジタル放送と同じような感覚で視聴されているということですね。
ただし、今度はOTTと地上デジタル放送を比較すると、OTTの方が専念視聴の割合が高くなります。例えば地上デジタル放送と同じコンテンツを流しているはずのTVerの方が、地上デジタル放送よりも専念視聴するユーザーが多いのです。恐らくオンデマンド形式の動画配信サービスの方が、ユーザーは観たいコンテンツを自ら選び取ることができるので、専念視聴の割合が高まるのだと思います。つまり同じ「半沢直樹」でも、視聴する手段が地上デジタル放送とTVerでは、ユーザー層も視聴形態も異なる可能性があります。

資料提供: The Trade Desk
さらに言えば、地上デジタル放送を録画した人が、果たしてどれだけしっかりとCMを視聴しているかという課題もあります。ユーザーが観たいときに、きちんと広告を表示し、かつターゲティング技術を活用できるAVODの優位性が今回の調査を通じて改めて浮き彫りになったと言えます。
CTVはマーケティングを変える
―「広告が嫌われる時代」と言われていますが、動画配信サービスにおいては視聴者が広告視聴を前向きにとらえていることも意外でした。

資料提供: The Trade Desk
若い世代が「広告と引き換えに無料でサービスを利用」という事業モデルに理解を持っていると考えられるのが一つ。また様々なデータが取得できるようになったことで、ユーザーの趣味嗜好に合った広告を出し分けできるようになったからだと想像します。今後は許諾したユーザーのデータをSSP経由でDSPが拾い上げ、広告会社がそれらのデータをより積極的に活用できるようになると、広告の許容度がさらに上がっていくでしょう。
―OTTに代表される動画広告が、テレビCMを超える日は来るのでしょうか。
CTVが今後どれだけ普及していくかにかかっています。一般論として、テレビCMの効果を測るデータは、広告会社が管理するリーチとフリークエンシー計測及び調査会社がまとめ上げるブランドリフト効果の調査結果などです。
ただし、これらのデータだけでは、宣伝した商品なりサービスの売上の増減との関連性が把握しきれません。テレビCMを打った後でウェブサイトの訪問数が上がった、オンライン購入が増えたということは分かるかもしれませんが、各ユーザーのカスタマージャーニー全体を見渡すことができない。だからこれまでマーケターは、テレビCM→ディスプレイ広告→ウェブサイト→コンバージョンといった各施策を段階的につなぎ合わせた「ファネル」の概念を用いてカスタマージャーニーの理解に努めてきました。
ところがCTVは、広告を放映するユーザー対象や気象条件などを細かく設定することで、認知媒体にも購入媒体にもなり得ます。従来のファネルという枠組みを取り払ってしまうような大きな可能性を秘めたCTVには大きな期待を抱いています。
The post 「動画配信サービス利用実態調査」から得た示唆とは-The Trade Deskはこう考える appeared first on Exchangewire Japan.
 先日行った調査では、動画広告の視聴完了をしたユーザーのブランドリフト値が視聴完了をしていないユーザーよりも大幅に高くなる結果になりました。
先日行った調査では、動画広告の視聴完了をしたユーザーのブランドリフト値が視聴完了をしていないユーザーよりも大幅に高くなる結果になりました。
 中川氏:TVer社としてのミッションは、当社を通らない販売チャネルも含め、包括的にTVer全体の広告事業を拡大していくことです。
中川氏:TVer社としてのミッションは、当社を通らない販売チャネルも含め、包括的にTVer全体の広告事業を拡大していくことです。 矢部氏:広告商品としてより魅力を高めていくうえでは、ユーザー数の規模が求められます。データを活用して精度や広告効果を高めていく上でも、このことは必須です。
矢部氏:広告商品としてより魅力を高めていくうえでは、ユーザー数の規模が求められます。データを活用して精度や広告効果を高めていく上でも、このことは必須です。 AppsFlyerへの参画を語るにあたって、まず私とAppsFlyerとの出会いからお話をさせてください。遡ること7年前。まだAppsFlyerの日本法人ができる前に、現アジアManaging Directorを務めるRonen Menseと話す機会がありました。その際にAppsFlyerのビジネスの説明とデモ画面を見せてもらい、アトリビューションツールの観点からプロダクトが非常に良くできており今でも鮮明に覚えているほど印象深いものでした。当時私はシンガポールでFacebook広告の市場拡大に関わっていた為チームを離れることはできなかったのですが、AppsFlyerのことはずっと頭に残っておりいつか機会があればと考えていました。
AppsFlyerへの参画を語るにあたって、まず私とAppsFlyerとの出会いからお話をさせてください。遡ること7年前。まだAppsFlyerの日本法人ができる前に、現アジアManaging Directorを務めるRonen Menseと話す機会がありました。その際にAppsFlyerのビジネスの説明とデモ画面を見せてもらい、アトリビューションツールの観点からプロダクトが非常に良くできており今でも鮮明に覚えているほど印象深いものでした。当時私はシンガポールでFacebook広告の市場拡大に関わっていた為チームを離れることはできなかったのですが、AppsFlyerのことはずっと頭に残っておりいつか機会があればと考えていました。 ここ10年ほどのデジタルマーケティングの歴史において、アトリビューションの仕組みとあり方にここまで注目が及んだことは初めてだと思います。そして、その中でAppsFlyerが変わらず取り組んできたユーザープライバシーへの取り組みについて、エコシステムの中にいる皆様に理解していただける、まさにそのタイミングがきました。
ここ10年ほどのデジタルマーケティングの歴史において、アトリビューションの仕組みとあり方にここまで注目が及んだことは初めてだと思います。そして、その中でAppsFlyerが変わらず取り組んできたユーザープライバシーへの取り組みについて、エコシステムの中にいる皆様に理解していただける、まさにそのタイミングがきました。

 LINE公式アカウントはマーケティングファネルで言うと比較的深い部分を担っているところに価値があると私たちは認識しております。LINE広告等でユーザーに広告主のサービスを幅広く認知させて、LINE公式アカウントで友だち登録をしてもらい、その後ユーザーとLINE公式アカウント上で広告主はコミュニケーションを取ることができます。LINE公式アカウントのコアバリューは、企業とユーザーとがOne to Oneでつながり、LINE公式アカウント上でやりとりをしながら、企業のサービスを届けることが出来るという点です。
LINE公式アカウントはマーケティングファネルで言うと比較的深い部分を担っているところに価値があると私たちは認識しております。LINE広告等でユーザーに広告主のサービスを幅広く認知させて、LINE公式アカウントで友だち登録をしてもらい、その後ユーザーとLINE公式アカウント上で広告主はコミュニケーションを取ることができます。LINE公式アカウントのコアバリューは、企業とユーザーとがOne to Oneでつながり、LINE公式アカウント上でやりとりをしながら、企業のサービスを届けることが出来るという点です。 LINEマーケットプレイスでは、LINE公式アカウントの運用サポートパックというものを提供しています。
LINEマーケットプレイスでは、LINE公式アカウントの運用サポートパックというものを提供しています。 メインはコンビニやドラッグストア、スーパーで商品を展開されているメーカー様です。
メインはコンビニやドラッグストア、スーパーで商品を展開されているメーカー様です。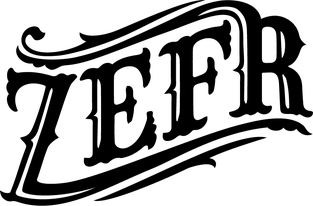
 杉山氏:三井物産はデジタルマーケティング領域で事業を進めていく中で、ここ数年は海外から先進的なデータ関連のソリューションやテクノロジーを持ってくるビジネスを進めています。これまでもクロスデバイスのTAPAD、ジオターゲティングのFactual(現:Foursquare)などの日本展開を支援していましたが、これらに続く新しいソリューションを探していました。
杉山氏:三井物産はデジタルマーケティング領域で事業を進めていく中で、ここ数年は海外から先進的なデータ関連のソリューションやテクノロジーを持ってくるビジネスを進めています。これまでもクロスデバイスのTAPAD、ジオターゲティングのFactual(現:Foursquare)などの日本展開を支援していましたが、これらに続く新しいソリューションを探していました。 ケニー氏:ZEFRは、クッキーに依存せずに、YouTube向け動画広告の配信面をコントロールすることが可能なプラットフォームです。日本においては現在YouTube向けのみですが、グローバルではFacebook向けの配信にも対応しており、将来的には日本でも利用できるようになる予定です。
ケニー氏:ZEFRは、クッキーに依存せずに、YouTube向け動画広告の配信面をコントロールすることが可能なプラットフォームです。日本においては現在YouTube向けのみですが、グローバルではFacebook向けの配信にも対応しており、将来的には日本でも利用できるようになる予定です。 ミサ氏:これを実現するにあたり、繰り返しになりますが、ZEFRはYouTubeの公認パートナーであることから、YouTube上にアップされている動画に大規模にアクセスすることが出来る権利を持っています。その中から該当するブランドが広告を配信するにふさわしい面のみを抽出し、ZEFR側がブランドにとってのプレミアムな広告在庫をリスト化します。
ミサ氏:これを実現するにあたり、繰り返しになりますが、ZEFRはYouTubeの公認パートナーであることから、YouTube上にアップされている動画に大規模にアクセスすることが出来る権利を持っています。その中から該当するブランドが広告を配信するにふさわしい面のみを抽出し、ZEFR側がブランドにとってのプレミアムな広告在庫をリスト化します。 ミリ氏:究極的には、YouTubeで動画広告を出稿している全てのお客様にお使いいただきたいと考えています。
ミリ氏:究極的には、YouTubeで動画広告を出稿している全てのお客様にお使いいただきたいと考えています。 佐藤氏:まず、ターゲティング配信における対応としては、ファーストパーティークッキーのリッチ化が一つのカギになります。IDを持つメディアは、これを増やしていくことで、情報を追加していくことにより、最終的にそのユーザーがログインするとターゲティングが可能になります。
佐藤氏:まず、ターゲティング配信における対応としては、ファーストパーティークッキーのリッチ化が一つのカギになります。IDを持つメディアは、これを増やしていくことで、情報を追加していくことにより、最終的にそのユーザーがログインするとターゲティングが可能になります。 小林氏: 2017年からコンテンツメディア価値研究会という組織をデジタルガレージが事務局となって立ち上げました。ここでは、世の中デジタル化が進み、プラットフォーマーが台頭していく中で、実際にコンテンツを作り出している、日本を代表するデジタルの一次メディアが今後どのようにしていくべきであるかということをテーマに研究活動を行ってきました。
小林氏: 2017年からコンテンツメディア価値研究会という組織をデジタルガレージが事務局となって立ち上げました。ここでは、世の中デジタル化が進み、プラットフォーマーが台頭していく中で、実際にコンテンツを作り出している、日本を代表するデジタルの一次メディアが今後どのようにしていくべきであるかということをテーマに研究活動を行ってきました。 基本的には一部の悪質なアフィリエイターたちが、小遣い稼ぎのために好き勝手しているからです。
基本的には一部の悪質なアフィリエイターたちが、小遣い稼ぎのために好き勝手しているからです。

 芝崎氏:2021年の4月にヤフーの組織体制が変更され、広告のプロダクト部門とメディア部門が一緒になり、同じ執行役員の下で活動することになりました。それに合わせて、私が広告事業領域の責任者という形でアサインを受け、現在は業務を行っております。
芝崎氏:2021年の4月にヤフーの組織体制が変更され、広告のプロダクト部門とメディア部門が一緒になり、同じ執行役員の下で活動することになりました。それに合わせて、私が広告事業領域の責任者という形でアサインを受け、現在は業務を行っております。
 田中氏:私は2021年の4月から運用型広告のサービスマネージャーを担当し、運用型広告に関する機能追加や精度改善等の責任者をしております。
田中氏:私は2021年の4月から運用型広告のサービスマネージャーを担当し、運用型広告に関する機能追加や精度改善等の責任者をしております。










